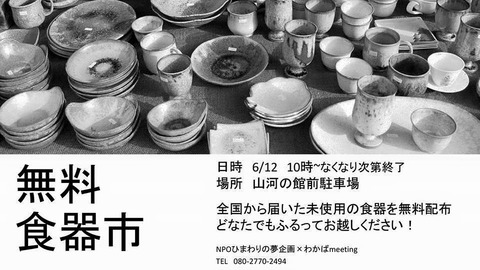<災害時におけるボランティア事情-36>
熊本地震の被災地に、梅雨前線が停滞し記録的な豪雨をもたらし、被害を拡大させています。現地からのレポートを送ります。
<6月21日現場レポート>
熊本地震から2ヶ月が過ぎ少し落ち着きを取り取り戻そうとしている中、被災者の心を打ち砕くかのような豪雨により、熊本県では観測史上4番目となる1時間150ミリの雨量を観測し、土砂崩れなどに巻き込まれ6人の尊いいのちが奪われました。いつもお世話になっている高野山関係の宇城市の寺院でも床上浸水の被害が出たという報告をお聞きしました。
西原村では、地震で緩んだところに大量の雨水が染み込み、至る所で土砂崩れが発生し、朝から雨も小康状態となり、ボランティアも住民さんと協力しながら、ブルーシートをかぶせたり、土嚢づくりをしたり、道を塞いだ土砂をかき分けたりと、一日中動き回りました。被災者の方からは「また振り出しだ」という落胆の声が聞こえてきました。この熊本地震の直後に出産したお母さんは、3人の小さな子どもを持ち、その大雨の日は石垣が崩れるギシギシする音を聞きながら不安な夜を過ごしたそうです。新築の自宅も地震による倒壊をまぬかれたものの、隣のお宅の石垣に地震により亀裂が入り、そこへ今回の大雨により土砂崩れが発生したのです。


崩壊の危険から守る擁壁にかぶせていたブルーシートが、強風に煽られ土嚢袋が切れてしまったその補修に追われるなど、先週に引き続き「UP GARAGE」の社員さんは着いて早々、大活躍でした。 


そして、唯一水が戻ってきた田んぼでは、田植えを終えたばかりでした。そこへこの大雨により、土砂が流入したり、あぜに亀裂が入り、水が流出したりして、被災者が前に歩み出そうとする心を無情にも打ち砕きました。 



今朝も雨が降り出していますが、これ以上被害が広がらないことを祈るばかりです。他の地域のみなさまもくれぐれもお気をつけください。